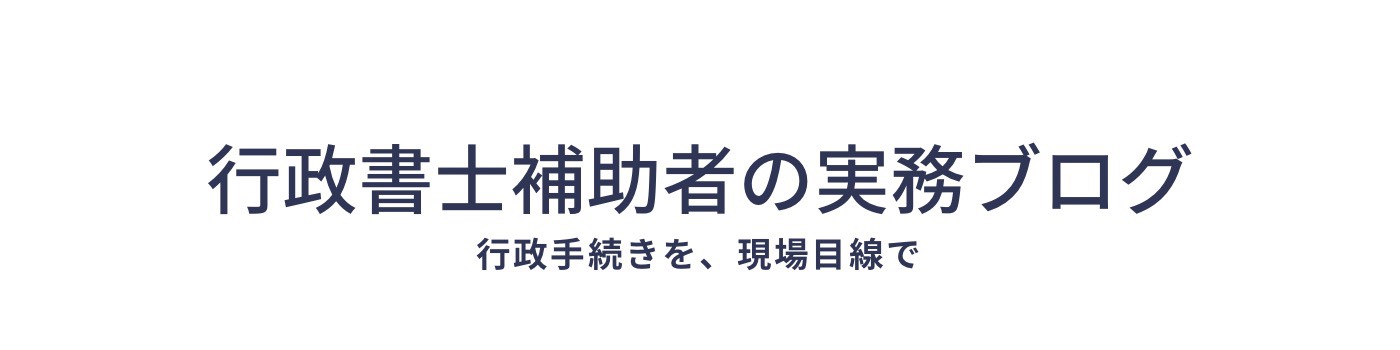株式会社を設立する際に必ず登場する「発起人」という言葉をご存じでしょうか。「発起人」=「取締役」や「役員」ではありません。本記事では、発起人の定義から具体的な役割、負うべき責任まで、会社設立に欠かせない情報を分かりやすく解説します。

発起人の基本知識
発起人とは何か?その定義を理解する
発起人とは、株式会社の設立に際して、設立時発行株式の引受人であるとともに、定款に記名押印をした者を指します。会社法第26条第1項において、株式会社を設立するには発起人が定款を作成し、その全員が署名または記名押印することが定められています。
簡潔に表現すると、発起人は会社設立のための企画者であり、設立手続きの中心的な役割を担う人物です。会社という組織を法的に成立させるため、様々な準備作業と法的手続きを行う責任者といえます。
発起人と取締役の違い
多くの方が混同しがちなのが「発起人」と「取締役」の違いです。この2つの役割は明確に異なります。
発起人の役割は、あくまで会社設立の手続き(企画、出資、定款作成など)を行うことです。会社が設立された後は、原則としてその役割は終了します。一方、取締役は会社が設立された後に、会社の業務執行や意思決定を行う機関です。
実務上は、発起人がそのまま設立後の会社の取締役に就任するケースが大半を占めます。しかし、法律上は発起人が必ずしも取締役にならなければいけないという決まりはありません。ただし、発起人が1人しかいない場合、その人が必然的に発起人兼取締役になることが一般的です。
端的に言えば、発起人は「会社をつくる人」であり、取締役は「会社を経営する人」という違いがあるのです。
発起人の人数に制限はあるのか
会社法上、発起人の人数に制限はありません。1人でも複数人でも発起人になることができます。
一人会社の場合は、その1人が発起人となり、同時に設立後の取締役も兼ねることになります。複数人で会社を設立する場合は、メンバー全員が発起人になることも可能ですし、一部のメンバーのみを発起人とすることもできます。
ただし、発起人の数が多ければ多いほど、意思決定に時間がかかったり、後述する責任の範囲が複雑になったりする可能性があります。実務的には、必要最小限の人数に絞ることが推奨されます。
発起人とは
- 人数に制限なし:会社を設立する際、発起人は1人でも可能ですし複数人で進めることもできます。
- 設立後の役員になることが多い:発起人が、そのまま設立後の会社の役員(取締役など)に就任するケースがほとんどです。
- 定款に必ず記載される:発起人の氏名や住所は、「定款に必ずに記載しなければならない項目」の一つです。
発起人の具体的な役割と義務
定款の作成と署名・押印
発起人の最も重要な役割の一つが、定款の作成です。定款とは、会社の組織や運営に関する基本的なルールを定めた文書のことで、いわば会社の憲法のようなものです。
定款には、必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」、定款に定めがなければ効力を生じない「相対的記載事項」、そして任意で記載できる「任意的記載事項」の3種類があります。
絶対的記載事項として、会社法第27条により以下の項目が定められています。
- 目的(会社が行う事業内容)
- 商号(会社の名称)
- 本店の所在地
- 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
- 発起人の氏名または名称及び住所
これらの事項のうち、一つでも欠けると定款は無効となります。
作成された定款には、発起人の全員が署名し、または記名押印する必要があります。この署名・押印によって、その人が正式に発起人として認められることになります。つまり、定款に署名していない者は、たとえ設立手続きに関与していても、法的には発起人とは認められません。
設立時発行株式の引受けと出資
発起人は、設立時発行株式を1株以上引き受けなければなりません。(会社法第25条第2項)つまり、発起人は必ず設立する会社の最初の株主となる必要があるのです。
株式の引受け後、発起人はその引き受けた株式について、出資に係る金銭の全額(資本金)を払い込む義務があります。払い込みは、発起人が定める払い込み先の銀行口座に資本金を入金することで行います。
会社設立前は社名を使って法人口座を開設できないため、資本金の払込に使用する口座は発起人の誰かの個人口座を使用することが一般的です。複数の発起人がいる場合、通常は代表者となる予定の発起人の口座を使用します。
払込が完了したら、払込証明書を作成します。具体的には、払込の内訳や資本金を集めるために使った口座を証明する通帳のコピーなどを用意し、設立登記の際に法務局へ提出します。
公証役場での定款認証手続き
定款を作成したら、次は公証役場で認証を受ける必要があります。定款認証とは、公証人が定款の記載内容を確認し、正当な手続きで作成されたことを証明する手続きです。
認証を受ける公証役場には場所的要件があります。会社の本店所在地を置く予定である都道府県内の公証役場で行わなければなりません。また、認証を行う公証人についても、会社の本店所在地を管轄する法務局または地方法務局に所属する公証人であることが必要です。
公証役場での認証に必要な書類は以下の通りです。
- 定款3通(会社保管用、法務局提出用、公証役場保管用)
- 発起人全員分の発行後3か月以内の印鑑登録証明書
- 発起人に法人が含まれている場合は、その法人の発行後3か月以内の登記簿謄本と代表者の印鑑証明書
- 実質的支配者の申告書
- 4万円分の収入印紙(紙の定款の場合。電子定款の場合は不要)
- 公証人への手数料(資本金の額により異なるが、5万円程度)
なお、電子定款を利用すると、4万円の収入印紙代が不要になるため、コスト削減のメリットがあります。電子定款に要するソフトの導入で数万円費用がかかるので、行政書士などの専門家に会社設立申請を依頼するほうがおすすめです。
設立登記申請の実施
定款認証が済んだら、次は法務局で設立登記申請を行います。設立登記とは、会社の設立を公的に記録し、法人格を取得するための手続きです。
本店所在地を管轄する法務局へ、以下の書類を提出します。
- 登記申請書
- 定款(公証役場で認証を受けたもの)
- 発起人の決定書または発起人会議事録
- 設立時取締役の就任承諾書
- 設立時取締役の印鑑証明書
- 資本金の払込証明書
- 印鑑届出書
- 登録免許税(15万円または資本金の0.7%のいずれか高い方)
登記申請が受理され、法務局での審査が完了すると、会社が正式に成立します。この登記申請日が会社の設立日となります。
発起人になれる人の資格要件
未成年者でも発起人になれるのか
未成年者(18歳未満の者)でも発起人になることは可能です。
ただし、民法上の制限行為能力者であるため、法定代理人(通常は親権者である両親)の同意が必要となります。同意なく未成年者が発起人となった場合、その行為は取り消される可能性があります。
実務上は、未成年者が発起人となるケースは稀であり、成人してから会社設立を行うことが推奨されます。
成年被後見人・被保佐人の場合
成年被後見人は、発起人になることができます。ただし、会社設立の手続きに関する法律行為(定款作成、出資など)には、成年後見人の同意や代理行為が必要となります。
被保佐人も発起人になることができますが、同様に保佐人の同意が必要となります。
これらの制度は、判断能力が不十分な方を保護するための制度ですので、後見人や保佐人が適切に関与することで、発起人としての役割を果たすことが可能です。
法人も発起人になれる
意外に思われる方もいるかもしれませんが、法人(会社や組織)も発起人になることができます。発起人は資格や員数に制限がないため、個人だけでなく法人も発起人となることが認められています。
法人が発起人として会社を設立する際には、新しく設立する会社の事業目的と、発起人となる法人の事業目的が関連している必要があります。これは、発起人である法人が適切な権限を持って新会社の設立に関与しているかを確認するためです。
法人が発起人となる場合、定款認証の際には、その法人の発行後3か月以内の登記簿謄本と代表者の印鑑証明書が必要となります。
外国人でも発起人になれる
外国人についても、発起人となることができます。国籍による制限はありません。
日本に住所登録(住民登録)がある外国人であれば、日本人と同様に印鑑登録ができますので、印鑑登録証明書により本人確認が可能になります。
住民登録をしていない外国人の場合は、印鑑証明書を取得できないため、代わりに「サイン証明書」を提出する必要があります。サイン証明書とは、本国の官憲(当該国の領事及び日本における権限がある官憲を含む)が作成した、署名が本人のものであることを証明する書類です。
外国人が会社を設立する場合、在留資格の問題も考慮する必要があります。会社設立後に日本で事業を行うには、「経営・管理」などの適切な在留資格が必要となりますので、事前に専門家に相談することをお勧めします。
破産者の発起人就任
破産者でも発起人になることは可能です。破産したことをもって発起人になれないという法律上の制限はありません。
ただし、現実問題として、破産者は金融機関からの融資を受けるのが困難であったり、取引先や顧客から信用を得るのが難しくなったりする可能性があります。会社設立後の事業運営に支障をきたす恐れもあるため、会社を設立する際は、司法書士や行政書士などの専門家に相談して、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。
発起人が負う法的責任
財産価額填補責任
現物出資または財産引受の対象となった財産の価額が、定款に記載された価額に著しく不足するとき、発起人はその不足額を会社に対して支払う義務を負います。(会社法第52条)
現物出資とは、金銭ではなく不動産や設備などの現物を出資することです。財産引受とは、会社が成立後に特定の財産を譲り受けることを約束することです。
これらの場合、発起人及び設立時取締役は、株式会社に対して連帯してその不足額を支払う義務を負います。ただし、発起設立において、検査役の調査を経た場合、または発起人及び設立時取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合には、現物出資者または財産の譲渡人である発起人を除き、この責任を免れることができます。
なお、現物出資者や財産の譲渡人である発起人については、検査役の調査を経た場合でも無過失責任を負います。これは、譲渡人は定款に記載された価額に見合う対価を得ているため、当然に不足分をてん補するべきという趣旨です。
出資の履行を仮装した場合の責任
発起人が出資の履行を仮装した場合、つまり実際には払い込んでいないのに払い込んだように見せかけた場合、発起人は会社に対して全額を支払う義務を負います。(会社法第52条の2)
仮装払込みに関与した発起人や設立時取締役も、連帯してこの責任を負います。
定款に記載した出資金は必ず実際に払い込まなければなりません。仮装払込みは重大な違反行為であり、後に発覚した場合、会社の信用を大きく損なうだけでなく、刑事罰の対象となる可能性もあります。
任務懈怠責任
発起人、設立時取締役または設立時監査役は、株式会社の設立についてその任務を怠ったとき、当該株式会社に対して、これによって生じた損害を賠償する責任を負います。(会社法第53条)
「任務を怠った」とは、発起人が会社設立の手続きを適切に行わなかった場合や、必要な注意を払わなかった場合などを指します。例えば、定款の記載事項に重大な誤りがあった、必要な許認可の取得を怠った、出資金の管理を不適切に行ったなどのケースが該当します。
会社に損害が発生した場合、発起人は金銭的な賠償責任を負うことになります。複数の発起人がいる場合、これらの者は連帯して責任を負います(会社法第54条)。
また、発起人、設立時取締役または設立時監査役がその職務を行うについて悪意または重大な過失があったときは、第三者に生じた損害についても賠償する責任を負います。
この任務懈怠責任は、総株主の同意がなければ免除することができません(会社法第55条)。これは、発起人の責任が重大であることを示しています。
疑似発起人の責任
実務上、注意が必要なのが「疑似発起人」の問題です。
募集設立においては、募集広告やその他書面等に賛同者として氏名を記載することを承諾すると、定款に署名していなくても発起人としての責任を負う場合があります。このような者を「疑似発起人」といいます。
会社設立に名前を貸すだけのつもりでも、法的には発起人と同様の責任を負う可能性があるため、安易に名前を貸すことは避けるべきです。
発起人設立と募集設立の違い
株式会社の設立方式には、「発起設立」と「募集設立」の2つがあります。
発起設立とは
発起設立とは、発起人が設立時に発行される全ての株式を引き受ける方式です(会社法第25条第1項第1号)。
一人会社や少人数の株主で会社を設立する場合に適した方式で、手続きが比較的シンプルです。現在、日本で設立される株式会社の大多数がこの発起設立の方式を採用しています。
募集設立とは
募集設立とは、発起人が設立時発行株式の一部のみを引き受け、残りの株式について他の引受人を募集する方式です(会社法第25条第1項第2号)。
多数の株主から資金を集めて会社を設立する場合に適した方式ですが、手続きが複雑で時間もかかります。設立時募集株式の引受人に対する責任など、発起人の責任も重くなる傾向があります。
どちらを選ぶべきか
実務上は、特別な理由がない限り発起設立を選択することが一般的です。手続きが簡便で、コストも抑えられるためです。
大規模な資金調達を伴う会社設立や、特定の投資家を募る場合には募集設立を検討することになりますが、その場合は専門家のサポートが必須といえるでしょう。
発起人の役割終了後
会社設立後の発起人の立場
会社が無事に設立されると、発起人の役割は基本的に終了します。ただし、発起人は設立時発行株式を引き受けているため、必ず会社の株主となります。
株主として、株主総会における議決権や剰余金の配当を受ける権利など、株主としての権利が付与されます。
発起人から取締役へ
実務上、発起人がそのまま設立後の会社の取締役に就任するケースがほとんどです。特に一人会社の場合、発起人=取締役=株主となることが一般的です。
ただし、法律上は発起人が必ずしも取締役にならなければならないという決まりはありません。発起人は会社設立の手続きを担当する役割であり、設立後の経営には関与しないという選択も可能です。
まとめ
発起人とは、株式会社の設立に際して定款に署名または記名押印した者であり、会社設立の企画者として重要な役割を担います。
発起人になるということは、単に名前を貸すだけではなく、法的に重大な責任を負うことを意味します。会社設立を検討されている方は、これらの責任を十分に理解した上で、慎重に進めることが重要です。
複雑な手続きや責任について不安がある場合は、行政書士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。適切なアドバイスを受けることで、スムーズかつ確実な会社設立が実現できます。