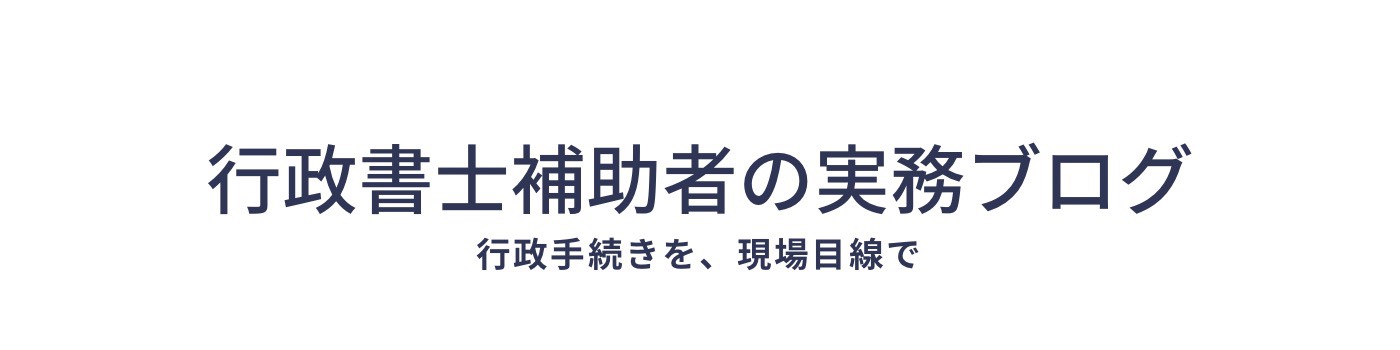宅地建物取引業とは?
宅地建物取引業(宅建業)とは、宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいいます。
宅地:単に建物が建っている土地だけでなく、建物の敷地に供される土地や、都市計画法で定められた用途地域内にある土地も含まれます。ただし、道路や公園、河川といった公共の用に供されている土地は除かれます。
売買: 宅地や建物を有償で譲渡することです。
交換: 宅地や建物を別の宅地や建物の交換することです。
媒介: 宅建業者が売主と買主の間に立ち、取引が円滑に進むように両者を引き合わせることです。契約締結の権限は持っていません。
代理: 宅建業者が依頼者の代理人として、契約締結の権限を与えられている状態です。依頼者に代わって、契約の相手方と交渉し、契約を締結することができます。
業:「行として行う行為」とは、不特定多数人を相手に、反復・継続してこれらの行為を行うことを意味します。
媒介と代理は似てるようですが大きな違いがあります。
それは契約締結の権限かあるかどうかです。
媒介・・契約締結の権限は持っていません。
代理・・契約締結の権限を与えられているので、相手と交渉ができます。
免許制度の目的と消費者保護
不動産取引は、多くの一般消費者にとって人生で一度か二度の高額な買い物です。専門知識が必要な一方で、不動産業者と消費者との間には大きな情報格差が存在します。 免許制度は、宅地建物取引業を営もうとする者に対して、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けることを義務付けることで、消費者の利益を保護し、適正な不動産取引を実現することを目的としています。 免許を受けた業者は以下の義務を負います。
- 重要事項説明の実施
- 契約書面の交付
- 営業保証金の供託または保証協会への加入
- 帳簿の備付けと保存
- 従業者名簿の作成と設置
これらの規制により、悪質な業者を排除し、消費者が安心して不動産取引を行える環境が整備されています。
宅建業にあたる場合、あたらない場合
宅建業に当たる場合としては自社所有の土地を分譲して、不特定多数の人に継続的に販売する行為や賃貸アパートのオーナーから管理を任され、入居者の募集・契約手続きを代行する行為(代理・媒介)があります。
宅建業に当たらない場合は引っ越しが決まったため、自分が住んでいた家を一度だけ売却する行為や自身が所有するアパートを、入居者と直接契約して貸す行為です。
表にすると以下になります。〇にあてはまる行為は宅建業に当てはまります。
| 自己物件 | 他人物件代理 | 他人物件媒介 | |
| 売買 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 交換 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 賃借 | ✖ | 〇 | 〇 |
具体的な事例
【免許が必要】
- 自社所有の土地を分譲して、不特定多数の人に継続的に販売する行為
- 賃貸アパートのオーナーから管理を任され、入居者の募集・契約手続きを代行する行為
- 中古物件を仕入れて、リフォーム後に転売する事業
- インターネットで継続的に不動産を売買する行為
【免許が不要】
- 引っ越しが決まったため、自分が住んでいた家を一度だけ売却する行為
- 自分が所有するアパートを、入居者と直接契約して貸す行為
- 親から相続した土地を売却する行為(一回限り)
- 自社ビルを自ら使用するために購入する行為
宅建業の申請先
宅建業を営むには、個人・法人を問わず、宅地建物取引業免許の申請をする必要があります。この免許は、事務所の所在地に応じて、都道府県知事または国土交通大臣に申請して取得します。
一つの都道府県内のみに事務所を設置する場合・・都道府県知事免許
二つ以上の都道府県に事務所を設置する場合・・国土交通大臣免許
大阪の知事免許の場合、申請先は大阪府庁です。
⼤阪府建築振興課 宅建業免許申請受付窓⼝
〒559-8555 ⼤阪市住之江区南港北1-14-16
⼤阪府咲洲庁舎
注意点:「事務所」とは、宅建業の業務を行う場所を指します。単なる登記上の本店所在地ではなく、実際に営業活動を行う拠点が該当します。
- 本店のみで営業 → 知事免許
- 本店+支店(同一都道府県内)→ 知事免許
- 本店+支店(異なる都道府県)→ 大臣免許
- 案内所や一時的な出張所は「事務所」に該当しません。
免許の有効期間は5年間で、引き続き事業を営む場合は更新が必要です。免許の有効期間満了日の90日前から30日前までに、免許の更新申請をする必要があります。
免許取得の要件
欠格要件に該当しないこと
宅地建物取引業法第5条第1項に定める欠格要件に該当する場合、免許を受けることができません。
主な欠格要件
- 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられた者、または宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた者で、その執行終了から5年を経過しない者
- 免許不正取得、情状が特に重い不正行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合、取消しから5年を経過しない者
- 免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し不正または著しく不当な行為をした者
- 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者
- 事務所に従業者5人に1人の割合で専任の宅地建物取引士を設置していない場合
- 法人の場合、役員のうちに上記のいずれかに該当する者がいる場合
特に注意すべき点
- 過去の犯罪歴だけでなく、民事的なトラブル(未払い、契約違反など)も審査対象
- 法人の場合、全役員(監査役を含む)が対象
- 相談役や顧問など、実質的に経営に関与している者も審査対象となる場合があります
事務所の形態要件
宅建業の事務所は、以下の要件を満たす必要があります。
独立性の要件
- 物理的に独立した空間であること
- 他の法人や個人と明確に区分されていること
- 独立して施錠できること
使用権限の要件
- 事務所を継続的に使用できる権限があること
- 賃貸の場合、賃貸借契約書で確認
- 使用貸借の場合、使用承諾書が必要な場合があります
不可とされる事例
- バーチャルオフィス
- レンタルオフィスの共有スペース
- シェアオフィスの非専有ブース
- 自宅の一部(独立性が確保できない場合)
可能とされる事例
- 自宅の一室(独立性が確保されている場合)
- 賃貸マンションの一室
- レンタルオフィスの専有個室
- 他社と同じビル内でも、明確に区分されていれば可
写真による確認 大阪府では、申請時に事務所の写真提出が求められます。
- 事務所入口の写真
- 事務所内部の写真
- 宅建業者票(標識)の掲示場所の写真
- 共用部分の写真(必要な場合)
専任の宅地建物取引士の設置
事務所には従業者5人に1人の割合で専任の宅地建物取引士を設置することが法律で義務付けられています。
専任性の要件 「専任」とは、次の2つの要件を満たすことを意味します。
- 常勤性:その事務所に常時勤務していること
- 週5日、1日8時間程度の勤務が目安
- パートタイマーでも要件を満たせば可能
- 専従性:宅建業の業務にもっぱら従事していること
- 他社の専任宅建士との兼任は不可
- 他の事業との兼業は原則不可(例外あり)
設置人数の計算
- 従業者5人につき1人以上
- 代表者本人が宅建士であれば、1人目にカウント可能
- 役員全員を従業者にカウントする(宅建業のみを営む場合)
- 事務職や経理担当者も従業者にカウント(宅建業のみを営む場合)
例:従業者が6人の場合
- 5人につき1人 → 最低2人の専任宅建士が必要
専任宅建士の要件確認
- 宅地建物取引士証の有効期限内であること
- 他社で専任として登録されていないこと
- 社会保険加入など、常勤性を証明できること
必要書類と申請手続き
法人申請の必要書類
法人が新規に免許を申請する場合、以下の書類が必要です。
基本書類
- 免許申請書(第一面から第五面)
- 登記されていないことの証明書(代表者・役員全員分)
- 身分証明書(代表者・役員全員分)
- 略歴書(代表者・役員全員分)
- 代表者等の連絡先に関する調書
- 誓約書
法人関係書類 7. 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 発行から3か月以内
- 目的欄に「宅地建物取引業」の記載が必要
- 定款
- 納税証明書(法人税)
- 資産に関する調書
- 直前決算書
専任宅建士関係書類 12. 専任の宅地建物取引士設置証明書 13. 宅地建物取引士証のコピー 14. 専任性を証明する書類(社会保険証のコピー、雇用契約書など)
事務所関係書類 15. 事務所の写真(カラー) 16. 事務所の図面 17. 賃貸借契約書のコピー(賃貸の場合) 18. 使用承諾書(必要な場合)
その他 19. 相談役・顧問に関する書類(該当者がいる場合) 20. 5%以上の株主に関する書類
令和6年5月25日からの変更点 専任の宅地建物取引士の『身分証明書』『登記されていないことの証明書』が不要となりました。
個人申請の必要書類
個人が新規に免許を申請する場合、法人と比べて以下の点が異なります。
法人との主な相違点
- 登記事項証明書、定款は不要
- 納税証明書は所得税
- 資産に関する調書(個人用)
- 決算書の代わりに確定申告書
その他は法人と同様
- 本人の登記されていないことの証明書
- 本人の身分証明書
- 略歴書
- 専任宅建士関係書類
- 事務所関係書類
申請から免許交付までの流れ
ステップ1:事前準備(1〜2週間)
- 事務所の確保
- 専任宅建士の確保
- 必要書類の収集
- 申請書類の作成
ステップ2:申請書類の提出
- 大阪府の場合:咲洲庁舎の建築振興課へ提出
- 提出部数:正本1部、副本1部の計2部
- 申請手数料:33,000円
ステップ3:審査
審査にかかる標準審査期間は、書類受付後5週間です(
審査内容:
- 欠格要件の確認
- 事務所の適格性確認
- 専任宅建士の専任性確認
- 資産要件の確認
ステップ4:免許通知 審査が終了すると、免許通知のハガキが郵送されます。
ステップ5:営業保証金の供託または保証協会への加入 免許を受け営業を開始するまでに主たる事務所については1,000万円、従たる事務所についてはその数ごとに500万円の総額を営業保証金として主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければなりません
ただし、宅地建物取引業保証協会の社員となった者は営業保証金を供託する必要はなく、これにかえて弁済業務保証金分担金として、主たる事務所については60万円、従たる事務所についてはその数ごとに30万円の総額を納付します。
ステップ6:営業開始 営業保証金の供託または保証協会への加入手続きが完了して、初めて営業を開始できます。
宅地建物取引士とは?
宅地建物取引士(宅建士)とは、宅地建物取引業法に基づいて定められた不動産取引の専門家です。国家資格であり、不動産取引における消費者の保護と、取引の公正・円滑化を目的としています。
宅建士になるには以下の手順です。
宅地建物取引士資格試験に合格する: 毎年1回10月に行われる試験に合格する必要があります。
受験資格に学歴や年齢の制限はありません。
登録手続きを行う: 試験に合格しただけでは「宅建士」とは名乗れません。
実務経験が2年以上あるか、または「登録実務講習」を受講・修了した上で、都道府県知事に登録手続きを行います。
宅地建物取引士証の交付を受ける: 登録が完了すると、「宅地建物取引士証」が交付され、初めて正式に宅建士として業務を行うことができます。
宅建士の主な役割と独占業務
宅建士は、不動産取引の現場で、専門知識を活かして重要な役割を担います。特に、宅建士にしか行うことができない独占業務が法律で定められています。
宅建士の役割
- 重要事項の説明(35条書面)
- 不動産の売買や賃貸借の契約前に、買主や借主に対して、その物件に関する重要な情報を書面で説明すします。
- 物件の所在地、面積、権利関係、法令上の制限、インフラ設備(電気、ガス、水道など)、契約解除の条件などを解説し、トラブルを未然に防ぐ役割があります。
- 重要事項説明書への記名
- 上記で説明した「重要事項説明書(35条書面)」に、宅建士として記名します。説明した内容に責任を持つことを証明します。
- 契約書への記名(37条書面)
- 取引が成立後に作成される契約書(37条書面)に、宅建士として記名します。契約内容に誤りがないことを確認し、契約の正確性を担保します。
宅建業を営む事務所には、従業員5人につき1人以上の割合で専任の宅建士を置くことが法律で義務付けられています。
宅建業許可申請を行政書士に依頼するメリット
1. 「時間」という最大の経営資源を確保できる
起業前後において、経営者にとって最も貴重なリソースは時間です。
宅建業の免許申請には、膨大な書類の準備が必要です。
- 身分証明書や登記されていないことの証明書の取得
- 事務所の形態を証明する写真や図面
- 略歴書や誓約書
- 納税証明書や決算書の整理
これらを不慣れな方が一から調べ、役所を回り、不備なく揃えるには、かなりの時間を要するとので、行政書士に依頼すれば、経営者の作業は「押印」と「数点の書類用意」だけに絞られます。
2. 事務所要件の「事前判定」で手戻りを防ぐ
- 「自宅兼事務所でも大丈夫か?」
- 「他の会社と相部屋(シェアオフィス)だけど許可は下りるか?」
- 「入り口から他の会社を通らずに自社スペースに行けるか?」
これらは自治体ごとに非常に細かい基準があり、もし基準を満たさずに賃貸契約を結んでしまうと、せっかく借りたのに免許が下りないという最悪の事態になりかねません。
行政書士は、契約前の段階で現地の写真や図面を確認し、保健所や土木事務所の審査基準に適合するかをプロの目で判定します。これにより、無駄な家賃の支払いや改装費用の発生を未然に防ぐことができます。
3. 保証協会への入会手続きもワンストップ
宅建業を開始するには、免許の通知が届くだけでは不十分です。営業保証金(1,000万円以上)を供託するか、保証協会(ハトマーク・ウサギマーク)に入会して分担金を納める必要があります。
多くの業者が後者の保証協会を選びますが、この入会手続きがまた煩雑です。
- 免許申請と並行して進めるスケジュール管理
- 保証協会独自の必要書類の作成
- 面接日程の調整
行政書士は、免許申請とセットでこれらの手続きを代行します。「免許は下りたのに、保証協会の手続きが遅れて営業開始できない」という空白期間を作らせない、最短ルートのスケジュール管理が可能です。
4. 専任の宅建士や欠格事由の法的チェック
- 役員に過去の不祥事がないか
- 専任の宅建士が他の会社で登録されたままになっていないか
- 常勤性の証明に不足はないか
もし虚偽や不備があると、免許が下りないだけでなく、最悪の場合は虚偽記載として重いペナルティを受けるリスクもあります。行政書士は法的な観点からこれらを事前にチェックし、クリーンな状態で申請を遂行します。
5. 5年後の更新、変更届のフォロー体制
- 5年ごとの更新申請(忘れると免許失効・無免許営業に!)
- 役員の変更、事務所の移転、専任の宅建士の交代時の変更届(30日以内など期限あり)
これらが発生するたびに一から手続きを調べるのは非効率です。一度行政書士に依頼しておけば、自社の履歴を把握している「法務のパートナー」として、期限管理や迅速な届出を任せることができます。
まとめ
宅建業を営むには免許を受けなければなりません。また、専任の宅建士が必要になります。
不動産取引は、一般の人にとって人生で一度きりの高額な買い物になることが多く、専門的な知識が不可欠です。しかし、不動産業者と一般消費者との間には、知識や情報の格差が大きく、悪質な業者に騙されたり、不当な契約を結ばされたりするリスクがあります。
宅建業を営む者に免許を義務付けることで消費者の利益を保護し、安心して不動産取引ができる環境を整備しています。
宅建業免許の取得をお考えの方は、当事務所でもご相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。あなたの不動産業開業が成功することを心よりお祈りしています。